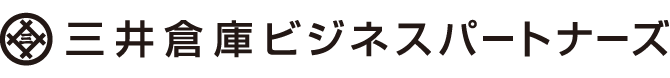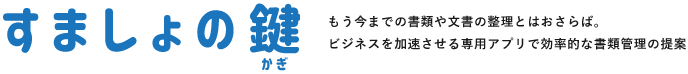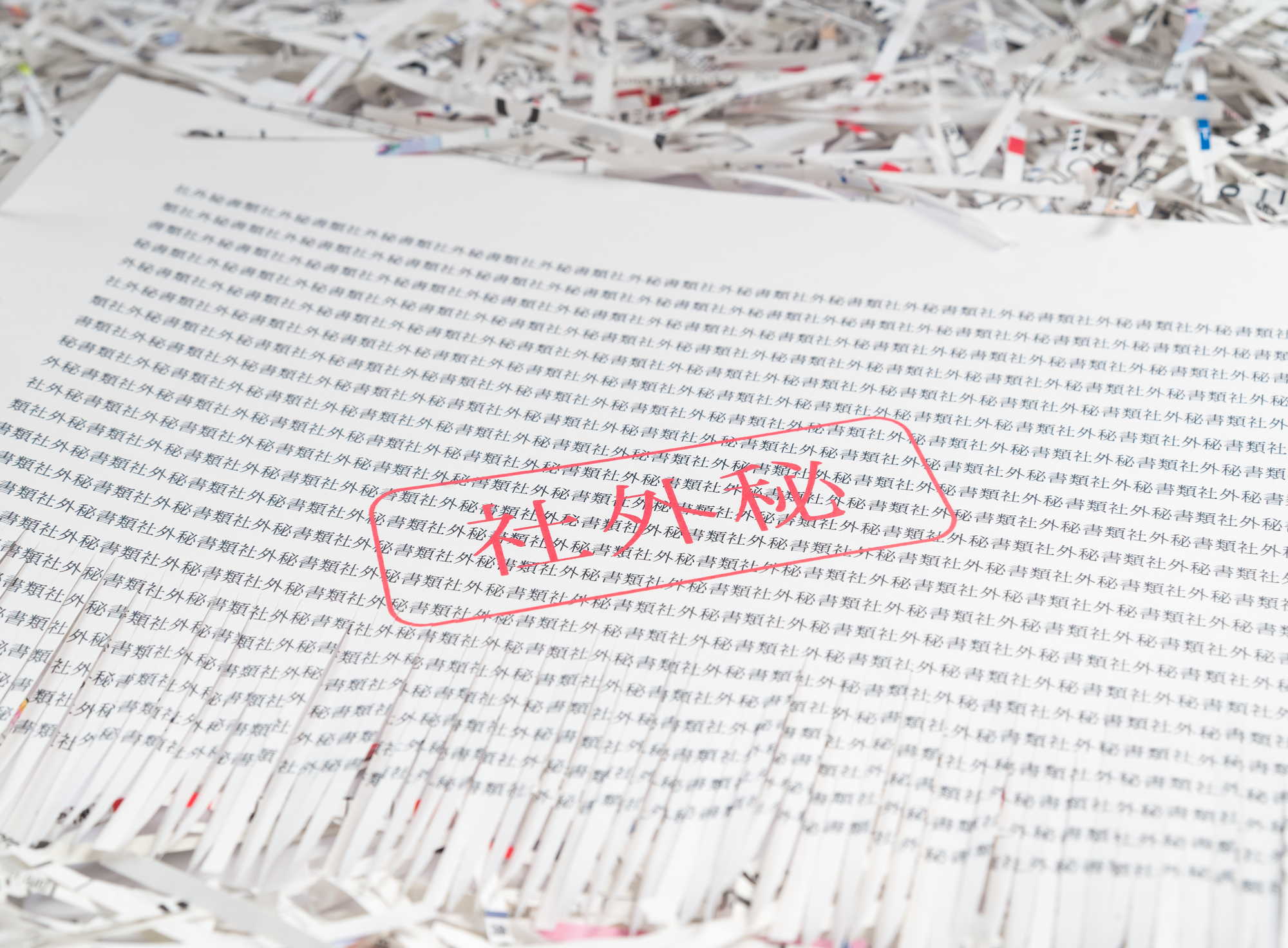電子化で後悔しないための「保管」と「電子化」の賢い使い分け
2025/11/10

近年、文書の電子化へのニーズは高まる一方で、「DXの一環として電子化を進めたい」といった声をよく耳にします。
電子化は、業務効率を劇的に向上させる強力な手段です。
しかし、「すべてを電子化する」という考え方が、必ずしも正しい選択とは限りません。
なぜなら、当初の目的から外れ、費用対効果の低いものになってしまう可能性があるからです。
本コラムでは、文書電子化で失敗しないための3つの重要なポイントをお伝えします。
ポイント1:閲覧頻度は電子化コストに見合っていますか?
電子化を検討しているお客様と、電子化サービスを提供する企業の営業担当者との間で、次のような会話があったとします。
お客様:「書庫の書類が全く整理できていないので、電子化して廃棄し、スペースを有効活用したいです。」
営業担当者:「廃棄を前提とした電子化ですね。」
お客様:「せっかく電子化するなら、文書管理システムも導入して、書類名だけでなく全文OCRで詳細に検索できるようにしたいです。また、タイトルだけでなく、種別、管轄部署、担当者、日付、時系列で管理もできればと考えています。」
営業担当者:「ちなみに、電子化の対象書類はどれくらいの頻度でご覧になりますか?」
お客様:「かなり頻繁に見ます。特に監査の時は、書庫をひっくり返して探すことになり負担です。」
営業担当者:「監査時以外で書類を活用するケースはありますか?」
お客様:「それ以外は、あまりないですね。」
かなり頻繁に閲覧すると考えていたお客様ですが、ヒアリングをしてみると実は頻繁ではなかったということがわかります。
このような場合、お客様の要望通りに見積もりを作成した結果、電子化費用が予想以上に高いと驚くかもしれません。
今度は、文書箱1箱において当社のサービスを利用した場合で費用感を考えてみましょう。
・当社の電子化サービス「スマート箱スキャン」:5万円/箱/回
・当社の保管サービス「スマート書庫」:100円/箱/月
入出庫がないと仮定した場合、電子化1箱にかかる費用は、その箱を約40年間保管する費用に相当します。
監査で使用する書類は、多くが法定保存期間が10年以内と定められています。
上記の商談のように、年に数回しか閲覧しない書類に多額の電子化コストをかけることは、明らかに費用対効果を損なうことになります。
本当に必要なのは、閲覧頻度に基づき「保管」と「電子化」を冷静に線引きすることです。
ポイント2:「内容物と保存期間の明確化」が文書管理のほとんどを完成させる
「すべてを電子化したい」という要望の根底には、「箱の中の書類が管理できていない」という不安があるのかもしれません。
これは、DXの流れに乗りたいという意識と、OCRによる検索性向上やデータ活用の魅力が後押ししているのでしょう。
しかし、「内容物と保存期間を明確にして外部保管に預ける」という行為は、実は文書管理のほとんどを解決します。
なぜなら、この行為によって「何を」「いつまで」「どこに」あるかが明確になり、以下の目的が達成できるからです。
・スペースの確保:法定保存期間のある書類の廃棄日を明確にして外部保管するだけで、スペースは削減できます。
・ルールの作成と維持:社内の文書管理ルールが崩れるのを防ぎ、煩雑な棚卸し作業が不要になります。
・検索性の向上:書類をリスト化して外部保管することで、箱の中に何が入っているかを把握でき、「探せない」という不安が解消されます。
高額な電子化費用をかけなくても、廃棄と外部保管を組み合わせるだけで、当初の目的である「スペース削減と自社管理工数の削減」は達成できます。
これは、電子化の前にまず取り組むべき、最も費用対効果の高い解決策と言えるでしょう。
ポイント3:電子化の成功は「継続性」と「書類の特性」にかかっている
電子化の大きな落とし穴は、電子化を初期費用、保管を継続費用と考えてしまうことです。
過去の書類をすべて電子化しても、今後発生する新しい書類をどう電子化するかを考えなければなりません。
自社内で実施することも可能ですが、見えないコストが発生します。
また、文書管理システムにも保守や更新といった維持コストがかかります。
ここで重要なのは、書類の「特性」に応じて段階的に管理方法を検討することです。
・日常的に閲覧したり、緊急な閲覧が必要な書類:電子化を検討すべきです。
・年に数回しか閲覧しないが、緊急性はない書類:まずは箱ごと保管を検討すべきです。
・年に数回閲覧するが、緊急性がある書類:必要な時にだけ電子化する「ODS(オンデマンドスキャン)」も選択肢に入ります。
すべてを「電子化」という一つの方法に集約するのではなく、「外部保管→目録管理→ODS→電子化」という選択肢の中から、その書類の利用頻度、重要度、法定保存期間に合わせて最適なサービスを組み合わせる。
これこそが、コストを抑え、運用を継続するために大切な考え方です。
ここまで読まれた方は電子化を否定するような内容に聞こえたかもしれませんが、そうではありません。
これらのポイントを聞いてなお電子化したいと思える書類は、本当に電子化すべき対象であり、活用頻度が高く、貴社の目的が明確にデータ活用に重点を置いているということになります。
単純に電子化ですべてが解決できると考えるのではなく、書類の利用状況を詳細に調査し、実態に合わせた最適な管理方法を選択することをおススメいたします。