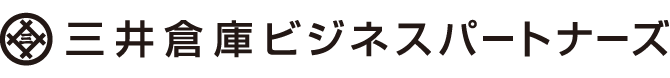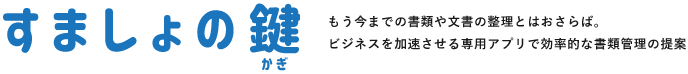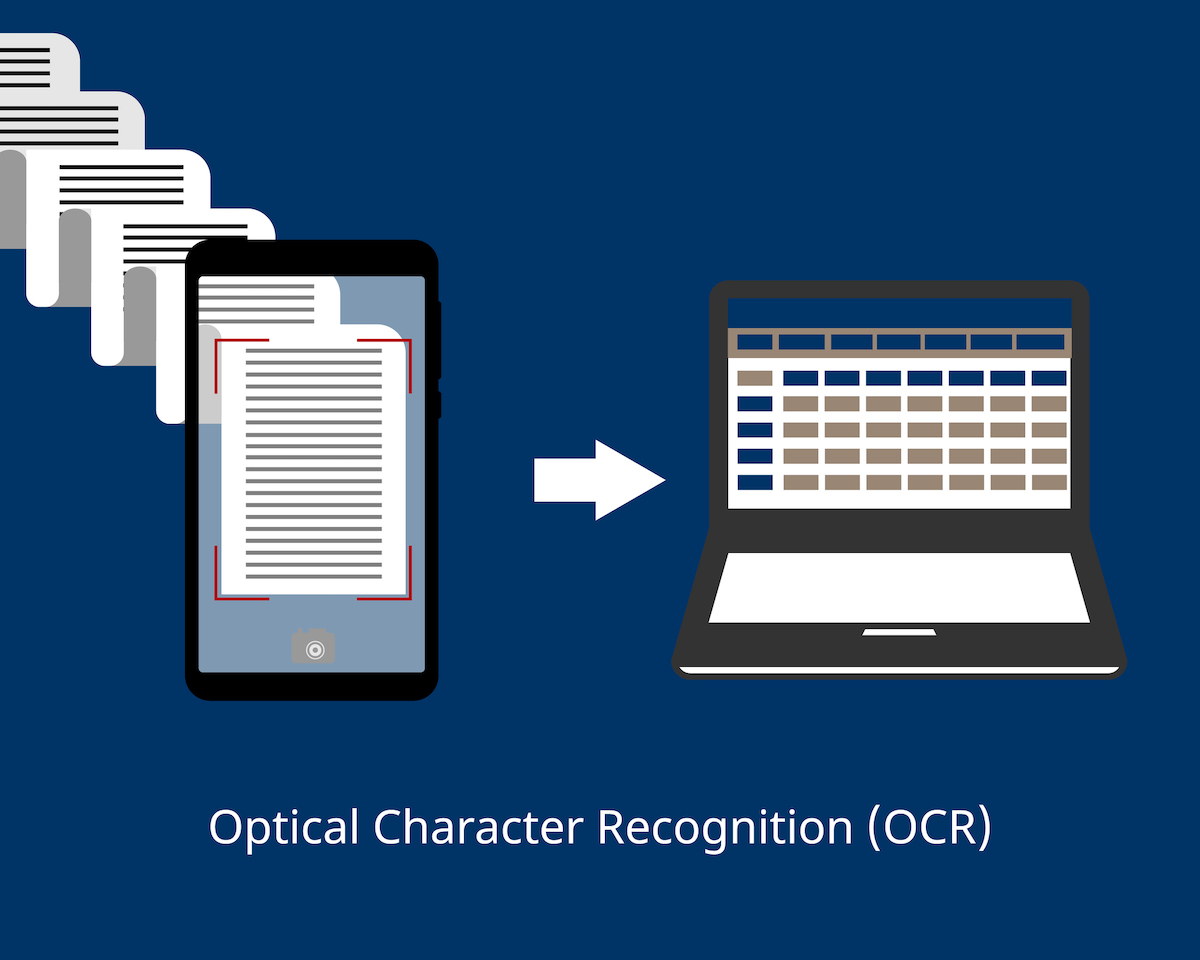社内書類の最適解:電子化と外部保管を組み合わせるハイブリッド戦略
2025/08/07

コストと効率を両立!書類の「電子化」と「外部保管」を賢く使い分ける方法
「社内書類を減らすなら、まずは電子化」――そう考える企業は多いでしょう。
しかし、電子化には初期コストがかかり、特に1年を過ぎるとほとんど見返す機会のない書類まで電子化しても、その費用が無駄になるのではないかという疑問も生じます。
実際、すべての書類を無差別に電子化することが常に最善の選択とは限りません。
本記事では、書類の「電子化」と「外部保管」それぞれの強みと最適な活用法を解説し、貴社にとって最も効率的でコスト効果の高い「ハイブリッド文書管理」の進め方をご紹介します。
Contents
ナレムコの法則
書類を整理するための仕分け作業において、もっとも重要な要素は「どのぐらいの頻度で見ることがあるのか」という視点であり、その実態を明らかにしているのがナレムコの法則です。
ナレムコの法則は、アメリカのNational Record Management Council (NAREMCO) によって調査・報告された経験則であり、文書の利用頻度に関する普遍的な事実を明らかにしています 。
この法則が示すのは、作成された文書の利用頻度が時間経過とともに急激に減少するというものです。
具体的には、文書が作成または収集されてから半年後にはその文書が利用される確率は約10%に低下し、1年後にはわずか1%にまで減少するとされています 。
この統計は、「書類が発生してから1年経過した書類の99%は利用されていない」という事実を浮き彫りにし、企業が物理的な文書の管理に費やすリソースの多くが無駄になっている可能性を示唆します。
「電子化」と「外部保管」:それぞれの強みと最適な活用法
ナレムコの法則を前提として、すべての書類を電子化するのではなく、書類の特性や利用頻度に応じて最適な管理方法を選択することが、コストと効率を両立させる鍵となります。
電子化のメリットと最適な書類
電子化は、主に「日常的に利用する書類」や「迅速なアクセスが必要な書類」に大きなメリットをもたらします。
・検索性とアクセシビリティの飛躍的向上:
電子化された文書は、キーワード検索やメタデータによる絞り込みで、必要な情報を瞬時に見つけ出すことができます 。
リモートワーク環境でも、場所を選ばずに文書にアクセス・共有できるため、業務の継続性や柔軟な働き方を支えます 。
・業務効率化とDX推進:
申請書や稟議書などのワークフローを電子化することで、承認プロセスが迅速化し、業務効率が向上します 。
AI-OCRやRPAとの連携により、さらなる自動化も期待でき、蓄積された文書情報をAIで分析し、経営判断に活用するといったDX推進の基盤となります 。
・法改正への確実な対応:
電子帳簿保存法により、電子取引データは電子のまま保存が義務付けられています 。電子化システムを導入することで、これらの法的要件を確実に満たすことができます。
〇電子化が最適な書類の例:
日常的に参照・更新される書類(例:社内規定、マニュアル、プロジェクト資料)
複数人での共同作業が必要な書類(例:企画書、報告書)
電子帳簿保存法で電子保存が義務付けられた電子取引データ(例:メールで受領した請求書PDF)
電子契約書など、最初から電子データで作成される書類
外部保管のメリットと最適な書類
「ほとんどの書類は1年を経過すると見る機会は減る」というナレムコの法則に従えば、閲覧頻度が低い書類や物理的な原本保管が必要な書類には、外部保管サービスが非常に効果的です。
・コストとスペースの最適化:
オフィス内の高価なスペースを書類保管に充てる代わりに、外部の専門倉庫に預けることで、賃料や管理コストを大幅に削減できます 。
削減したスペースは、会議室やリフレッシュスペースなど、より生産的な用途に活用できます 。
・長期保存と法令遵守:
会社法で10年、法人税法で7年(欠損金繰越控除を受ける場合は10年)など、長期の保存義務がある書類は多く存在します 。
外部保管サービスは、これらの書類を適切な環境で安全に保管し、保存期間管理をサポートします 。
・強固なセキュリティと災害対策:
専門の書類保管倉庫は、免震・耐震構造、耐火設備、24時間監視カメラ、入退室管理、温湿度管理など、厳重なセキュリティ対策が施されています 。
これにより、情報漏洩や災害による滅失のリスクを低減できます 。
・機密文書の安全な廃棄:
電子化後の紙原本や保存期間が過ぎた機密文書は、情報漏洩リスクを伴います。
外部保管サービスは、溶解処理や破砕処理など、情報漏洩リスクを最小限に抑えた専門的な廃棄サービスを提供し、廃棄証明書の発行も可能です 。
〇外部保管が最適な書類の例:
法的に長期保存が義務付けられているが、日常的な閲覧頻度が低い書類(例:会計帳簿、決算関係書類、株主総会議事録)
物理的な原本保管が必要な書類(例:一部の契約書、手書きの仕訳帳など)
過去の大量のアーカイブ文書
機密性が高く、厳重な物理的セキュリティが必要な書類
ハイブリッド文書管理で実現する最適な書類ライフサイクル
最も効果的なのは、書類の種類、重要度、閲覧頻度、法的要件、そしてコストを総合的に考慮し、物理保管とデジタル化を組み合わせる「ハイブリッド文書管理」です 。
現状把握と目標設定
まず、社内に存在する紙文書の種類、量、保管場所、利用頻度、保存期間(法定保存期間を含む)を洗い出します 。
その上で、「オフィススペースの削減」「業務効率化」「法改正対応」など、具体的なペーパーレス化の目的を明確にし、全社で共有します 。
書類の分類と適切な管理方法の選択
洗い出した書類を以下の基準で分類し、それぞれに最適な管理方法を割り当てます。
・高頻度で利用する書類:電子化を優先し、文書管理システムやクラウドストレージで管理します 。
・低頻度だが長期保存が必要な書類:外部の書類保管サービスに預け、オフィススペースを解放します 。
ナレムコの法則に従って、発生当年度内に利用する機会が想定される場合は、発生当年度内は社内のキャビネットに保管することも検討します。
・物理的な原本保管が必須な書類:外部保管サービスで厳重に管理します 。
保存期間が過ぎた書類:機密文書廃棄サービスを利用し、安全かつ確実に処分します 。
外部サービスの活用
自社だけで全ての文書管理を行うのは、コストやリソースの面で非効率な場合があります。
文書電子化代行サービス:大量の過去文書や、自社でのスキャニングが難しい書類は、専門業者に電子化を委託することで、効率的にデジタル化を進められます 。
書類保管サービス:物理保管が必要な書類や、閲覧頻度の低い書類を預けることで、オフィススペースを有効活用し、管理の手間とコストを削減します 。多くのサービスがWeb管理システムを提供しており、必要な時に迅速な取り出しが可能です 。
運用ルールの策定と社内への周知
電子化と外部保管を組み合わせた新しい文書管理体制を円滑に進めるためには、明確なルール作りと従業員への徹底した周知が不可欠です。
書類の種類ごとの保存形式、ファイル名規則、アクセス権限、保存期間、廃棄ルールなどを定め、定期的な研修会を通じて従業員の理解を深めましょう 。
結論:戦略的なハイブリッドアプローチで未来を拓く
社内書類のペーパーレス化は、単に紙をなくすことではありません。電子化と外部保管のメリットを最大限に引き出し、それぞれのデメリットを補完し合う「ハイブリッド文書管理」こそが、現代企業にとって最も現実的かつ効果的な戦略です。
貴社の書類管理を見直す際、閲覧頻度や重要度に応じた最適な管理方法を選択することで、コスト削減、業務効率化、情報セキュリティ強化、そしてDX推進という多岐にわたるメリットを享受できるでしょう。戦略的な文書管理は、企業の持続的な成長を支える強固な基盤となります。
三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社
・サービス一覧 https://www.mbp-co.net/service
・サービスに関するお問合せ https://www.mbp-co.net/contact