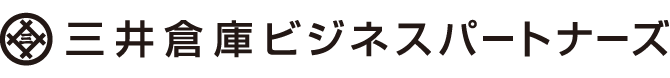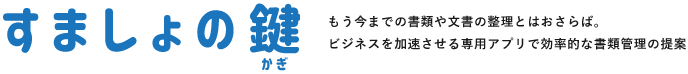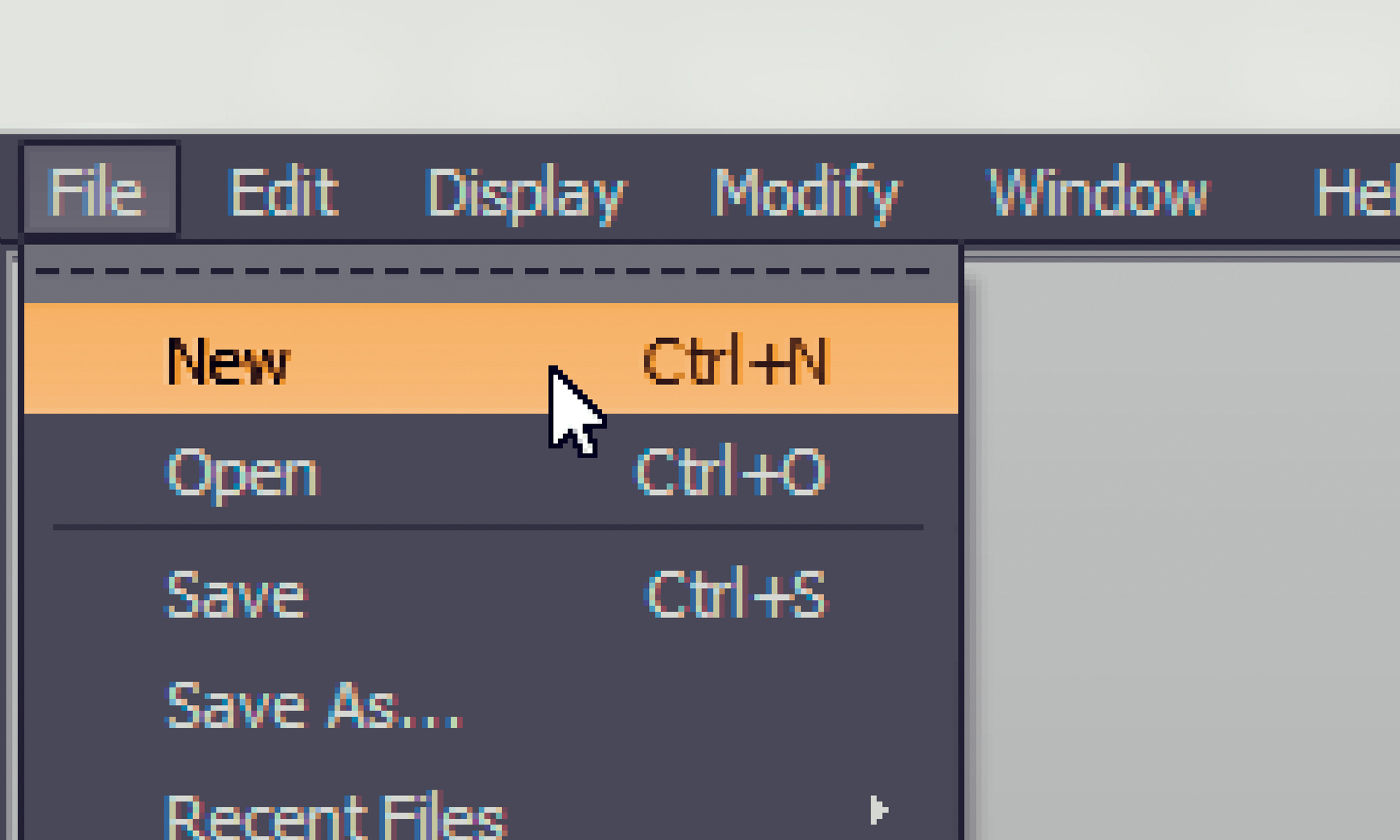書類の保存年限はどう決める?企業に求められる保存ルールの管理と廃棄のコツ
2025/09/02

企業の業務で日々発生する膨大な量の文書。
これらをいつまで保管すべきか、そしてどのように廃棄すべきかという課題に直面しています。
特に法律で保存期間が定められている「法定保存文書」の場合、そのルールを怠るとコンプライアンス違反や法令違反となるリスクに直結します。
一方で、「どの書類をいつまで保管するのか明確でない」「廃棄の判断が曖昧で、必要な文書を誤って破棄してしまった」といった管理不備によるトラブルも少なくありません。
また、保存ルールを定めないまま書類を積み重ねていけば、オフィス内の保管スペースはあっという間に圧迫されてしまい、物理的なスペースだけでなく、必要な情報へのアクセスに時間がかかり、業務効率の低下にもつながります。
このような背景から、企業には文書の保存年限を明確に定め、そのルールに従って適切に保管・廃棄を行う「文書のライフサイクル」を徹底することが求められています。
この記事では、文書の保存年限をどのように決定し、どのように管理・廃棄していくかについて、具体的な方法を解説します。
Contents
まずは「法定保存文書」を把握する
文書の保存年限を定める上で、最も重要なのが法律によって保存の期間が義務付けられている「法定保存文書」を正確に把握することです。
法定保存文書は、主に税法、商法、会社法などで定められており、その種類によって保存期間が異なります。
・ 法人税法:帳簿書類や決算関係書類は7年間
・ 会社法:会計帳簿や事業報告などの重要書類は10年間
・労働基準法:労働者名簿や賃金台帳などは5年間(当分の間は3年間)
これらの法定保存期間を遵守することは、企業のコンプライアンスを維持する上で不可欠です。
万が一、税務調査などで必要な文書が提示できなければ、追徴課税や罰則の対象となる可能性もあります。
まずは自社で発生する文書のうち、どれが法定保存文書にあたるのかを洗い出し、それぞれの保存期間をリストアップすることから始めましょう。
法定保存文書の種類や保存期間を一覧で確認したい方は、ぜひ当社の「文書保存年限表」をご活用ください。
https://www.mbp-co.net/hokankikan
「法定保存文書」以外の保存期間を決定する
法定保存文書のリストアップが完了したら、次に法定保存期間が定められていない文書の保存期間を定めます。
これらの文書は、業務の継続性や企業の独自ルールに基づいて以下のように分類し、保存期間を決定するのがよいでしょう。
・永久保存:定款、株主総会議事録、知的財産権に関する書類など、企業の根幹に関わる文書。
・重要文書(10年程度):契約書、稟議書など、法的なトラブルに備えて長期保管が必要な文書。民法の消滅時効期間(10年)を目安にするとよいでしょう。
・一般文書(1~5年):業務報告書、会議資料など、業務の経過や判断の根拠となる文書。
・短期保存文書(1年未満):社内連絡文書、業務メモなど、一時的に参照するだけでよい文書。
このように、文書の重要度や利用頻度などを考慮し、保存期間を細かく設定することで、不必要な文書をオフィスに抱え込むリスクを減らすことができます。
文書管理規程の策定と周知徹底
文書の保存年限を定めただけでは、管理が形骸化してしまう可能性があります。
そこで、すべての従業員が共通のルールで文書を扱えるように、文書管理規程を策定することが重要です。
文書管理規程には、以下の項目を盛り込むと良いでしょう。
・文書の分類方法と保存年限
・保管方法とセキュリティ対策
・廃棄のタイミングと方法
・文書管理の責任者
・文書の私有の禁止
・各「文書のライフサイクル」段階での管理
・文書の電子化・ペーパーレス化の推進
・ 規程の改廃と所管部門
作成した規程は、社内全体に周知徹底することが大切です。
社内研修やマニュアル配布などを通じて、従業員一人ひとりがルールを理解し、実践できる環境を整えましょう。
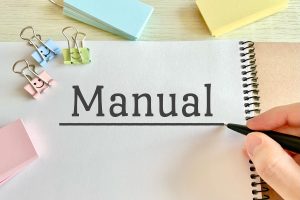
適切な保管と効率的な運用方法
文書管理規程を策定したら、次はルールに従って文書を適切に保管し、効率的に運用する仕組みを構築します。
・ 紙文書の管理:ファイリングのルールを統一し、保管場所を明確にしましょう。保管スペースを有効的に利用する為には、外部の文書管理サービスを利用し、文書を倉庫に預ける方法を検討するのも1つです。
・電子文書の管理:ファイル名やフォルダのネーミングの規則を統一することで、より検索性を高めることができます。文書管理システムやクラウドストレージを活用すれば、権限設定によるセキュリティ管理やバージョン管理も容易です。
廃棄のタイミングと方法を明確にする
文書のライフサイクルの最終段階である「廃棄」は、情報漏洩のリスクを伴うため、特に慎重に行う必要があります。
・廃棄のタイミング: 保存年限が到来した文書は、定期的に廃棄作業を行います。年に1回など、廃棄する時期をあらかじめ決めておくと、効率的に作業を進められます。
・廃棄方法: 紙文書は、シュレッダーにかける、溶解処理を業者に依頼するなど、復元不可能な方法で廃棄します。特に機密情報を含む文書は、信頼できる業者に委託することが重要です。電子文書も、データを完全に消去する専用ソフトを利用したり、物理的に記憶媒体を破壊したりするなど、適切な方法で廃棄する必要があります。
廃棄の際は、必ず廃棄する文書のリストを作成し、責任者が承認した上で実行するプロセスを設けるようにしましょう。
また保存期間を過ぎたからといって安易に廃棄するのではなく、「将来的に経営判断に役立つか」また「データ分析の基盤となるか」といった後のビジネスにどう活用出来るかという視点で廃棄の可否を判断するルールことも大切です。
定期的な見直しと改善
文書管理のルールは一度決めたら終わりではありません。
事業内容の変化や法改正、組織体制の変更などに応じて、定期的な見直しと改善が必要です。
年に一度は文書管理規程の内容をチェックし、現状に合っているか確認しましょう。
また、従業員から「このルールは使いにくい」「もっと良い方法はないか」といった意見を積極的に収集することも大切です。

まとめ
文書の保存年限を適切に管理することは、企業のコンプライアンスを維持し、業務効率を向上させる上で不可欠です。
・法定保存文書の保存期間を正確に把握する。
・法定保存文書以外の保存期間を重要度に応じて定める。
・文書管理規程を策定し、社内全体に周知徹底する。
・紙文書・電子文書それぞれの適切な保管・運用方法を確立する。
・情報漏洩を防ぐため、廃棄のタイミングと方法を明確にする。
・デジタル化を推進し、効率的な文書管理を実現する。
・定期的な見直しと改善で、常に最適な状態を保つ。
これらのステップを踏まえ、自社にとって最適な文書管理ルールを構築し、徹底していくことで、文書管理の課題は大きく改善されるはずです。
三井倉庫ビジネスパートナーズが提供する「スマート書庫のサービス」は、お預かりした紙書類の保存期限を文書管理システムにて簡単に行えます。
スマート書庫のシステムに入力していただいた保管期限が近づくとお客様へ自動で通知が届きます。
書類の管理状況を把握し、廃棄のタイミングを逃す心配もありません!
三井倉庫のスマート書庫
【書類保管.com】文書・書類管理サービス:三井倉庫スマート書庫
自社の文書保存年限を今すぐ確認したい方は、ぜひ無料の「文書保存年限表」をご活用ください。
「文書保存年限表」をダウンロードする